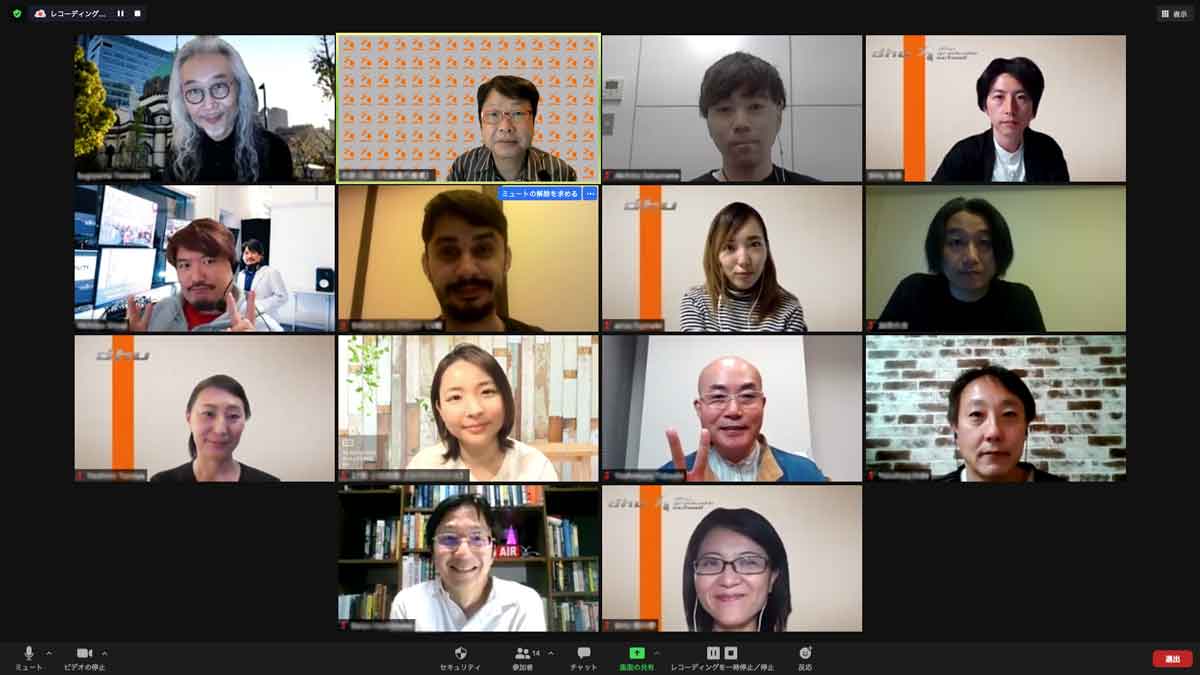デジタルハリウッド大学 研究紀要『DHU JOURNAL Vol.07 2020』研究論文発表会(2020年11月26日開催)参加レポート
2020年11月26日に開催された「デジタルハリウッド大学 研究紀要『DHU JOURNAL Vol.07 2020』研究論文発表会」に、参加された方から寄せられたレポートをご紹介いたします。

~はじめに~
去る2020年11月26日、デジタルハリウッド大学の研究紀要『DHU JOURNAL Vol.7 2020』に掲載された研究論文の発表会が、完全オンラインイベントとしてZoom上で開催された。
それを傍聴した一個人として非常に面白く感じる内容だったので、あえて主観的な感想を交えて紹介してみたい。
ありきたりな感想かもしれないが、まず一言で言うと「ユニーク」という印象だろうか。
もちろん、安易に独特であればいいと言うわけではなく、詳しくはこの研究紀要の編集幹事である木原民雄教授の論文『マルチメディア通信と分散処理研究領域における論文価値の意識調査』(情報処理学会第27回マルチメディア通信と分散処理ワークショップ論文集, pp.21–27, 2019)を読んでもらえると良いが、「独創性」の強さは必ずしも他者への「波及効果」の高さとイコールではない。
論文というアウトプットは、研究者としての自分の思考をまとめて記録する媒体であると同時に、他者への創発を生み出す最初のステップだと言える。
論文を書くことの大切さ、言い換えると研究するということの大切さを考えれば、誰もやっていないことを探すのではなく、自分が興味を持つことを探す、興味を持ったことを追求する姿勢こそが、重要だということは腑に落ちる。
発表会の最後に杉山学長もコメントしていたが、今後さらに深掘りしていけば面白い研究成果を生み出せそうな、あるいは、将来的に新しいビジネスも生み出せそうな発表がいくつもあったと感じた。
他人がこれまで全くやっていないこと、というのは意外と少ない。しかし、時代と共に技術が変わり、文化が変わり、様式が変わると、そこには「これまでにないなにか」が同時に誕生している。それはすなわち、あらたな研究対象が自然発生していると言うことだ。
これまでにない視座を提示されたことなどによるアカデミックな意味での知的興奮と、そこから生まれ出てくるものが、新たなサムシングを確立していきそうな予感に基づく情緒的興奮の双方を併せ持つという点で、この研究論文発表会は実に興味深い催しとなっていた。
また、この発表会は通常の学会のように「論文プレゼンテーションの場」ではなく、あくまでも論文を読んでもらうためのトリガーを提供し、著者と傍聴者、相互の知的活性化をはかるオンラインイベントとして開催されていた。各発表の時間は短く、テキストチャットやオンラインの質疑も簡潔で、良い意味で削ぎ落とされた内容に落とし込まれていると感じた。
各発表の紹介
<記憶に残る2020年に未来へ繋げる記録を残す 〜2020年夏、教員へのアンケートから〜>
杉山 知之 デジタルハリウッド大学 学長
発表の最初は特別寄稿として、「ニューノーマル」という概念に関する杉山学長の考察である。
激動の年となった2020年を変革へのチャンスと捉えた上で、どんなことをこれからの社会のノーマルとしたいか?について各教員にアンケートを取った杉山学長は、集めたアンケート結果が、社会、ビジネス、コンテンツ、教育の4つのテーマに分類できることを発見し、各分野における主要キーワードの出現頻度から、それぞれのテーマの方向性を考察している。
紀要には全アンケートの回答文が掲載されているのでぜひ、目を通して頂きたいが、(もちろんDHUは教育機関であるので)教育システムにおいてのニューノーマルとは何か?を深く考えさせられる内容となっている。
DHUは株式会社立大学という、ユニークな教育機関の先駆者と言える存在であるが、そのDHUが、COVID-19で一気に加速され始めたニューノーマルの時代において、有形・無形の双方において、新たな教育のあり方を探る先駆けとなっていることは、至極当然なのかもしれない。
そして、この教員アンケートを通じて、「オンラインでどこまでできるか?」を追求できたと同時に、「リアル」の場が欲しいことはなにか?を改めて確認できたことからも、今後のDHUにおける「学びの場」としてのクオリティが、オンライン/オフラインともに、大きく向上して行くであろう事が強く予感できた内容だった。
<人工自我の基本設計>
光吉 俊二 東京大学大学院工学系研究科 特任准教授
従来の数学概念に囚われない「切り算と重ね算」という発想をベースに、独創的な光吉演算子を駆使する独自の数学的理論で、AIに自我そして感情を持たせるという困難な課題にチャレンジしている光吉氏は、その試みの中で、「自我には道徳が必要である」ということに気づき、『人工自我に、いかにして道徳を持たせるか?』と、自らの研究テーマを発展させている。
さらには、機械学習/深層学習などではカバーできない「創発」をAIに持たせる事や、ベクトル値関数通信によって、AIに対して高い次元での道徳学習を可能にさせると言った研究など、一般にイメージされるAI研究と比べて遙かに独創的な視点から世界をとらえていることが見て取れる。
すでに、これらの独自理論に基づき、ノイマン型コンピュータ上で量子効果を実現する、この関数量子ゲート型コンピュータによる全く新しいAIについて、実用化を目指してテストを開始されているそうであるので、その成果にも大きく期待したい。
<デジタルハリウッド大学の日本人学生の英語力の背景>
江幡 真貴子 デジタルハリウッド大学 准教授
日本人学生と主要アジア諸国の学生との基礎的な英語力の格差、平たく言えば日本人学生の英語力が群を抜いて低いことに気づいた江幡氏は、その要因として、外国語(英語)の学習開始年齢/英語授業内で読む量/授業中の英語教員と本人の使用言語/授業外での英語使用頻度の4つが、英語能力判定試験のスコアに影響を及ぼしているのではないかという仮説を立て、その調査を行った。
結論から言えば、驚いたことに4つの仮説のうち学校での英語教育に関する3つのパラメーターが、学生の英語力にほとんど影響を及ぼしていないことを江幡氏は発見する。
その詳細は紀要を読んで頂くとして、一般的に予想される結果と異なる結果が出たことで、新しい知見が生じつつあると見受けられた。むしろ、予想と違う結果が出ることこそ、新たなひらめき、創発を生み出す研究の醍醐味の一つかもしれないと感じる発表だった。
<シーンベースのVR音響における上下定位の再現性向上に関する研究>
坂本 昭人 デジタルハリウッド大学 助教
VRコンテンツの普及が進みつつある中でも、360度動画における視点移動と音像定位の連動をより高水準にすると言う、コンテンツ制作の最前線にいる人物ならではの研究。
そのために、現状では再現性の低い『上下の視点移動による音の定位変化』の再現をいかに向上させるかに実証実験的に取り組んだ結果である。
野鳥観察を行う人にはよく知られていることだが、立体的な木立の中で鳴いている鳥がどこにいるか、音だけを頼りに位置を推定するのは案外に難しい。
これは坂本助教が論説の中で述べている通り、基本的に地表型の生物である人間は左右の定位には敏感でも上下の定位には鈍感だからだ。
新しいコンテンツ制作手法の提案という事で、今後の進化が楽しみな研究と思えた。
<ストレスでAIエージェントの行動を駆りたてることのプロトタイピング>
ブランセ マイケル デジタルハリウッド大学 助教
昨今、大きな市場となっている3Dゲームにおける『AIエージェント』の動きを、より高度にするために、ストレスを与えてエージェントの行動を刺激し方向付けるというユニークな研究である。
3Dゲームの多くがプレイヤーとゲーム内キャラクターとの「闘争」をテーマに構築されている中で、キャラクター(AIエージェント)の「感情」に注目し、その変化をゲーム要素に取り入れている作品が非常に少ないと言うブランセ氏は、キャラクターの動きに多様性を持たせるために、AIエージェントにストレスを与えて、アクションを動機づけることが有効ではないかという仮説に基づくプロトタイピングを行った。
今後、ゲーム世界における多彩な要素をストレス要因に設定することで、プレイヤーとの、より感情的なインタラクションが可能なAIエージェントを実現すると同時に、キャラクターのアクションに複雑な、そして感情に基づくトリガーを持たせることが可能になりそうだ。
<コロナ禍に伸長するNetflixによる映画市場の変化の考察>
因藤 靖久 デジタルハリウッド大学 メディアサイエンス研究所 研究員
映画というコンテンツの供給において、「配信」というスタイルがどのように市場に変化をもたらしているかを考察した研究である。
コロナ禍の時代において配信モデルを提供する企業が大きく売り上げを伸ばしていることはいかにも当然のように思えるが、実はそれ以前に、配信モデルが映画という市場の構造やパワーバランス自体を変えつつあったことが明らかにされている。
一見当たり前のように思える変化にも、そこに至るまでのプレイヤーの思惑や市場での綱引きの結果であることを、改めて考えさせられた考察だった。
<ドラマ『ネット興亡記』の制作プロデュース>
鈴木 宏昭 デジタルハリウッド大学 メディアサイエンス研究所 研究員
ドラマ『ネット興亡記』のプロデューサーである鈴木氏のメディアミックス〜すなわち複合的なチャンネルに渡るコンテンツのプロモーションにおいて、実に意欲的な取り組みが行われており、その制作のモチベーションが、単なる配信サービス向けコンテンツ制作にとどまっていなかったことが見て取れる。
インターネットの特性を存分に活用することで、一方的な「発信」にとどまらないコンテンツのプロデュースとプロモーションが実現する可能性を垣間見ることができる報告だった。
<浮世絵が小津安二郎の映画の表現形式に与えた影響に関する研究>
エブギン シェムセッディン デジタルハリウッド大学大学院 院生
小津安二郎監督の映画表現において、浮世絵が与えた影響を考察した面白い研究である。言うまでも無く、日本映画界を代表する映画監督と言える小津安二郎の作品やその技法については多くの人々が考察を重ねており、彼に関する書籍も数多く出版されている。
その中で、留学生であるエブギン氏が浮世絵と映画という、一見、特に関連性のなさそうな題材に視覚的な共通点を見いだし、その中から『日本的』と言われるビジュアルに、普遍的なフォーマットがあるのではないかという考察が生まれたことは非常に興味深い。
また、こうした分析を小津安二郎作品に限らず、またそのフレームを浮世絵に限らず拡げていくことで、映像コンテンツの新たなフォーマットを見いだすことが可能になるかもしれないと感じさせた。今後深掘りされていくことを期待したい。
<ギターレッスンのためのギタースケールダイアグラムを自動生成する アプリケーションの開発>
加茂 文吉 日本工学院八王子専門学校ミュージックカレッジ/デジタルハリウッド大学大学院 院生
ギターの演奏技術において重要な「スケール」の習得に多くの初心者がつまずいていることや、1:nという標準的な音楽教室の指導スタイル、学習者の「勘」に頼った練習方法などに限界を感じた加茂氏が独自の理論と知見を元に、スケール学習アプリケーション 「TASCALE」を開発した意図と経緯が述べられている。
初心者が音楽理論を学ばずとも創作や演奏に集中できるというメリットと共に、オンラインでの演奏技術習得が容易になる、あるいは教える側の視点からすれば、より広範囲の生徒に対して指導を提供することができるという点にも、オリジナリティの高い、将来性を感じる研究だった。
また、音楽分野に限らず、指導教員と学生の心理的関係と個別最適化の実現においても、新たな知見が得られそうな感触があった研究であった。
<オンライン授業におけるアバターを活用した個別最適化>
小林 英恵 デジタルハリウッド大学大学院 院生
オンラインコミュニケーションにおけるアバターは、素顔を隠す「仮面」という理解をされている事が多いだろう。
しかし、数年前からオンライン小学校を作りたいという構想を抱いていた小林氏は、アバターによって対面学習における子供の心理的障壁を取り除くことが可能になり、その結果、自由な発言を促すことで個別最適化を実現できるのではないか、というユニークな視点から研究を進めており、実際に小学校教員として子供の人間関係と学習をつぶさに見てきた人物ならではの発想が感じられる。
また、今回の研究では、オンライン授業においてアバターに限らず、「実写」「顔写真」「画像」「表示名のみ」を対象に加えて学生へのアンケートを実施しており、非常に興味深い結果を得られている。
児童心理に限らず、ビデオやチャットなども含めて対面コミュニケーションそのものが内包する問題なども今後の検討課題として見えてきており、この知見をさらに積み重ねていくことで、将来的にオンライン授業の学習性向上を大きく期待できるのではないかという可能性を感じた。
<デジタルハリウッド大学新入生研修 -完全オンライン実施報告->
田宮 よしみ デジタルハリウッド大学 学生支援グループ
この報告は実にDHUらしい、新入生への研修をオンラインで行ったという内容である。
ただし、単なるオンライン研修であれば、どこの企業や教育機関でも取り組んでいる話であるが、この実施内容の要点は、本来実施する予定であった「旅行型の研修」の質的代替をいかにオンラインで実現するかという視点で取り組んだことにある。
通常どおりの旅行型研修であれば、団体旅行という「動く閉鎖空間」ならではの集中力の維持や、参加者同士の親密性向上などを期待できるわけだが、その代わりに、新入生約300人が五日間に渡って集中的にオンライン作業を行うことで、十分にリアル研修旅行の代替となり得るオンライン研修のメソッドが開発されたようだ。
なお、この際に制作された電子書籍「コロナ後の未来を考える」は、出版(一般公開)されることを前提としており、その点でも参加した新入生に高いモチベーションを与えられているように思える。
<ポストコロナ時代のオープンキャンパス -オンライン開催の実態と効果についての一考察->
藤ノ木 有沙 デジタルハリウッド大学 入試広報グループ
言うまでも無く、大学における学生募集の一大イベントと言えばオープンキャンパスである。
今年の3月頃までは、国内におけるCOVID-19の影響が未だよく見えていなかったこともあり、各大学のオープンキャンパス実施方針はバラバラだった様だが、DHUが迅速にオープンキャンパスをオンライン開催する方向に舵を切ったのは、柔軟性の高い教育機関ならではの意思決定の早さだと思える。
この報告では、急遽オンライン開催方針となった春のオープンキャンパスに続き、初夏、夏と3回のオープンキャンパスを経て、開催のたびにソフトウェア的なノウハウがどんどん蓄積されていき、オンラインならではの特性を活かしつつ、「ライブイベント性」と「インタラクティブ性」を高めていった様子が見て取れた。
結論として、DHUのオープンキャンパスは、単なる「イベント中継」や「発信・配信」ではなく、オープンキャンパスというインタラクティブな番組の提供へと進化していると言えるだろう。
<デジタルハリウッド大学デジタルコミュニケーション学部におけるオンライン教育導入プロセス>
楢木野 綾子 デジタルハリウッド大学 大学事務局 副部長
報告の中で、COVID-19の影響によって全授業のオンライン化に踏み込んだ2020年を「第二の開校年度」と捉えるほどのインパクトがあったことが示唆されていたが、その対応においては強烈なプレッシャーと苛烈な準備作業があったことは想像に難くない。
そうした中、授業のオンライン化に当たって、多くの教員が能動的にデジタルキャンパスの実現に向けて取り組んでいった様子や、多彩な知見・ノウハウが蓄積されていった様子が報告内容から見て取れる。
いくつか『今後の課題』も挙げられているが、そうした課題を発見したこと自体も、DHUが今後デジタルキャンパス化をさらに推進していく上での重要な知見であり、敢えて言うならば他教育機関に対する優位性を形成していくものだと思われる。
そして、こうした取り組みがあってこそ、今回の 研究紀要のオンライン発表会が実現しているのだと感じられた。
~おわりに~
COVID-19をきっかけに社会は大きく変容しつつあるが、今回の研究紀要の内容にも、その影響は色濃く反映されている。
社会が急速かつ劇的に変化するときは苦痛だけでなく、必ず新しい取り組みを試すチャンスが生じる。DHUの教職員・研究員・院生・学生と立場はそれぞれ違っていても、生じた創発を追求したことの重要なアウトプットが、研究論文として形を成している。
他にも、本発表会でのプレゼンテーションは行われなかったが、今回の発表の元となった研究紀要『DHU JOURNAL Vol.7 2020』には、独創的な研究や報告が数多く掲載されているので、ぜひご覧頂きたい。そこには、各々の研究内容の面白さだけにとどまらず、そうしたユニークな研究への意欲や取り組みを支える、研究機関としてのDHUが大きく羽ばたこうとしている姿が見て取れるはずだ。
(KH記)